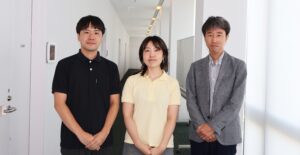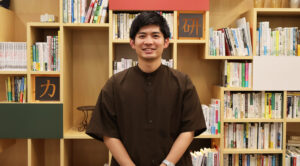南海電気鉄道株式会社南海電鉄 事業戦略部に聞く——社外越境×事業創出の仕組み「beyond the Border」は、どのように始まり、どのように推進されているのか
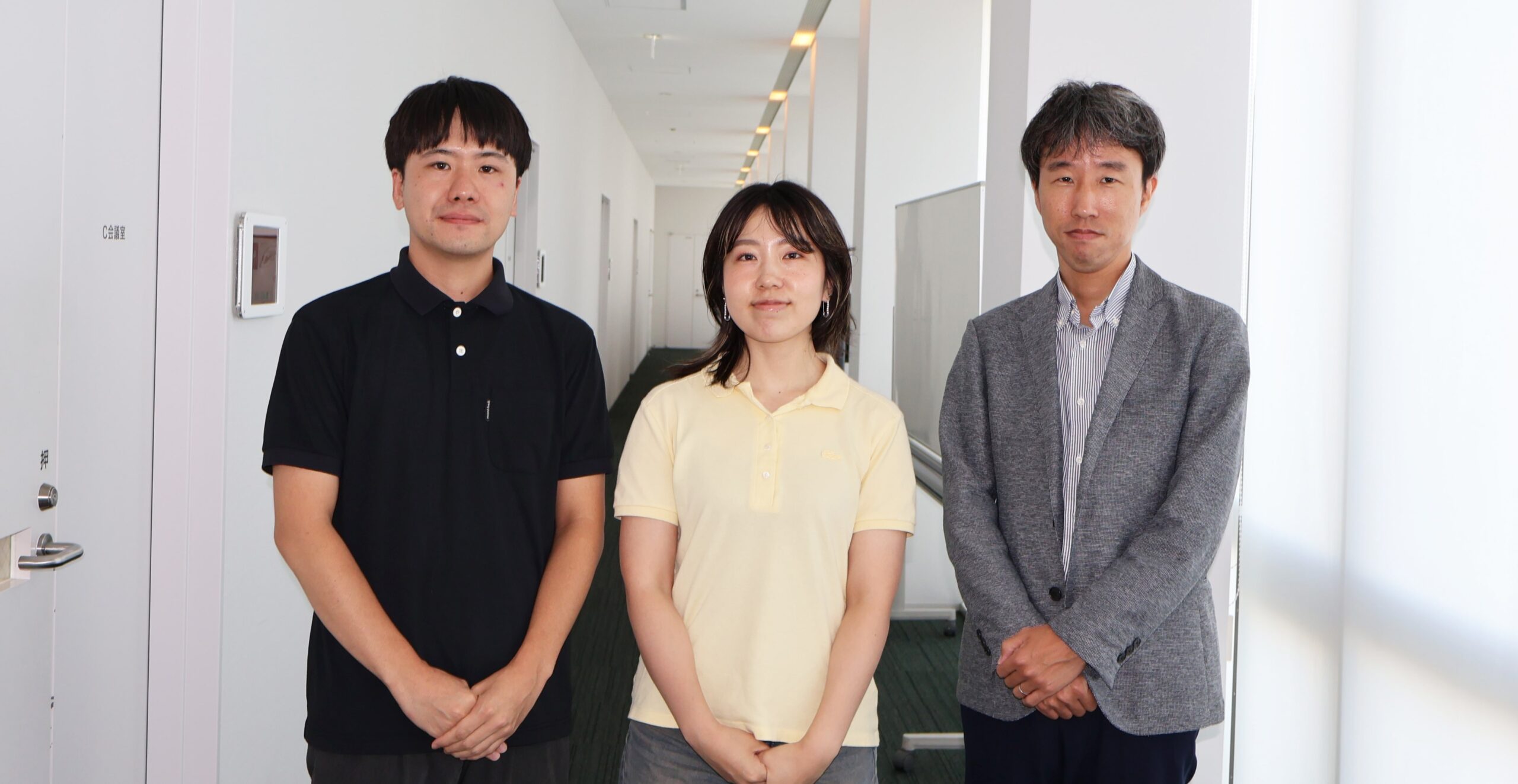
鉄道・不動産という安定基盤の上に、次なる収益の柱をどう築くか。人口減少やモビリティの変革など、鉄道会社を取り巻く環境は大きく変わりつつあります。南海電気鉄道株式会社(以下、文中では「南海電鉄」と表記)は、来年度の鉄道事業の分社化を見据え、経営戦略の要に「未来探索=新規事業創出」を掲げました。
2019年に社内向けにプログラムを開始し、2022年からは社外人財を対象とする「beyond the Border」を本格始動。採択された事業の推進者を社員として迎え、事業責任を担ってもらうという踏み込みは、国内でも先進的な取り組みです。
本記事では、事業戦略部の入江さん(全体写真:右)、渡邊さん(全体写真:真ん中)、山崎さん(全体写真:左)に、「beyond the Border」の誕生背景、運営の要諦、成果と課題、そして今後の展望を伺いました。
「未来探索」を担う南海電鉄事業戦略部と新規事業の位置づけ
まずは自己紹介からお願いします。部署の概要と、それぞれのミッションについて教えてください。
入江さん :
「事業戦略部は、南海グループの中期経営計画で掲げる未来探索、つまり鉄道や不動産以外の新たな収益の柱の創出に取り組む部門です。私はこの部の中で新規分野開拓を担当するチームの課長をしています。」
渡邊さん:
「2025年4月に経営戦略室の一部門になりました。これまでの組織とは異なり財務・経営戦略・サステナビリティ部門と横並びになり、連携がしやすくなりました。私はゼロから新規事業を創る仕組みを企画・運営し、自ら事業推進を行う役割を担っています。」
山崎さん :
「私はプログラムの設計・運営や事業開発の伴走などの事務局業務と、新規分野開拓に向けた市場探索を担当しています。」

会社として新規事業はどう位置づけられているのでしょうか?
入江さん :
「鉄道事業の成長の限界が見えつつある中で、2026年4月には分社化が控えています。不動産と合わせても企業価値の持続的な向上には限界があるため、2019年から新規事業創出を本格的に始め、今年度を初年度とする中期経営計画でも継続して取り組む重要なミッションになっています。」
社外人財向けプログラム「beyond the Border」の仕組みと運営
社内向けと社外向け、2つのプログラムについて教えてください。
渡邊さん:
事業創出支援プログラムは、2019年に社内向けかつ手上げ式での事業創出を目的にスタートしました。 “事業は人がつくる”を信条に、延べ60名がチャレンジし、本社社員の約1割が参加しました。現在は一時的に実施を見合わせていますが、将来の核となる事業創出を主目的とし、結果として人財育成にも繋がる施策として位置づけています。
社外向け「beyond the Border」は2022年11月に1期をスタートしました。社内だけで新規事業を生み出すには限界があるという問題意識から、外部の人財と共に事業をつくることを目的に設計されたプログラムです。最大の特徴は、最終的に採択された人財を南海電鉄の社員として迎え入れ、事業推進者になってもらう点にあります。
その後は立ち上げた新会社に出向し社長になる(出向起業)、子会社の責任者を務める、あるいは既存部門で新規事業を推進するなど、多様な“出口”を用意していることが大きな特長です。事業の性質や人財の志向に応じて最適な形を設計することで、本人の挑戦を最大限に後押しできる仕組みになっています。
山崎さん:
「beyond the Border」という名称には“常識や組織の境界を越えていく”という想いを込めています。社内や社外といった線引きを一度取り払い、最適な人財と資源を結び直すことを前提にした制度です。南海電鉄という枠に閉じるかたちではなく、外に開いたかたちで新規事業を進める、その意思を表しています。
社外人財活用に至った背景や社内の調整プロセスを教えてください。
渡邊さん:
事業創出支援プログラムは2019年発足の当初から「事業創出」を主目的に実施をしてきました。一方、社内人財のマインド醸成や事業創りにおける知識習得には一定以上の工数を要してしまうことが反省及び課題としてあげられたため、スピード感をもって事業開発を進めて成果を出すこと、そして、外部の血を入れてイノベーション文化の醸成を加速させることを狙い「beyond the Border」をスタートさせました。
最終的に社外の人財を雇用するという出口に対しては、人事からの理解も早く、『人財は全社共通の課題。1年伴走しながら見極められるなら、採用として合理的。加えて、新しい人財を“追加で迎える”という発想であれば、社内の既存組織を削るわけではないため軋轢も起きにくい。むしろ、事業創出経験のある人財を採用できる』といった点に、高い期待値を持っていただき、特に採用過程において前向きかつ迅速に協力してくれました。

募集にあたってどのような工夫をされ、その結果どのくらいが次のステージに進んだのでしょうか?
渡邊さん:
1期(2022年)はFacebookなどのWeb広告のみで募集し、50件の応募を集めました。ただし、質的な課題も見えてきました。
そこで2期(2023年)は関西に加えて、首都圏・九州など関西圏外にも積極的に足を運び、インキュベーション施設やイベントで登壇したり、直接声をかける“営業型”の手法を取り入れました。その結果、70件の応募があり、属性も会社員が約8割、残りはフリーランスや起業家と幅が広がり、アイデアや人財の質が向上しました。地域も関西が6〜7割、関東が3〜4割、北海道からの応募もありました。
さらに募集段階から月1回『メンタリング体験会』を開催し、応募者にプログラムを体感してもらえる場を設けたのも特徴です。こうした工夫の結果、ステージ1に進んだのは1期が50件中5件、2期が70件中7件と、いずれも約1割程度でした。
プログラムを支える仕組みや、運営上の課題・改善について教えてください。
山崎さん:
過去のプログラムでは、期間を通じて、外部メンターに週1回のメンタリングをお願いしていました。また、ステージ2以降は1案件あたり上限300万円の検証費などを支給し、さらに南海電鉄のアセットやリソース(検証フィールドやヒアリング先など)も可能な限り提供する仕組みにしました。
渡邊さん:
一方で運営面の課題もありました。ターゲット母数の少なさや、副業前提による離脱リスクです。また、1期では参加者同士の交流が希薄で学び合いが進みにくいという反省もありました。そこで2期では交流する機会も一定設け、支援体制とあわせて“仲間から学べる環境”を整えることで、継続率や学習速度の向上につなげることができました。
応募者のモチベーションや、そこから生まれた成果について教えてください。
渡邊さん:
応募者の大きなモチベーションは、自分が責任者として事業をつくれることです。独立ほどリスクは高くなく、南海電鉄のブランド力やネットワークを活かして検証をスピーディに進められる点も魅力であると感じています。さらにテーマフリーで応募でき、鉄道や不動産といった当社の既存領域にとらわれず挑戦できる点も好評でした。
実際、2期では2名が採択され、2025年4月に『株式会社yuppa』『株式会社メドエックス』を設立しました。製薬や食品業界出身など、通常の採用では出会えない人財とつながることができています。特に印象的だったのは、1期で落選した方が2期で再挑戦し、採択に至ったケースです。
また、この取り組み自体も評価され、『beyond the Border』は第13回日本HRチャレンジ大賞 採用部門で優秀賞を受賞しました。事業案と人財を同時に獲得できる新しい採用手段として高く評価いただいております。
今後の展望と企業へのメッセージ
今後どのように進化させたいですか?
渡邊さん:
beyond the Borderを継続しつつ、今後は南海電鉄グループ全体の事業探索インフラとして位置づけていきたいと考えています。社内・社外プログラムを区別せず一体的に運営し、互いの強みを融合させながら、より短期間で新規事業を生み出せる体制を整えていく予定です。
入江さん:
未来探索の文化を3〜5年で根付かせ、10年後にも続く新規事業創出の仕組みにしていきたいと考えています。新たな成長エンジンとなる事業を1つでも多く生み出していくことを目指しています。

同様の社外向けプログラムを考える企業へのアドバイスは?
山崎さん :
「beyond the Border」は、社外の方々と意見交換を重ねながら形にしてきた仕組みです。今後も、新規事業関連のプログラムを実施・検討されている事業会社とはライバルではなく仲間として一緒にエコシステムを形成・拡大していきたいと考えています。これまでの経験やノウハウをお話することもできますのでご興味があれば、ぜひお気軽にお声がけいただければと思います。
次回開催は決まっていますか?
山崎さん :
「詳細は未定ですが、今期中の開催を予定しています。情報は南海電鉄のイノベーションサイト『Fly beyond』やFacebookで発信します。自分の手で南海グループの次なる事業をつくりたいという方はぜひご注目ください。」
・Fly beyond 公式サイト
https://startup-nankai.com/
・Fly beyond Facebook
https://www.facebook.com/profile.php?id=100057413350994&locale=ja_JP