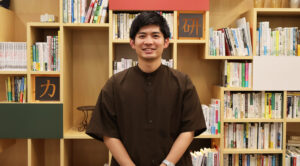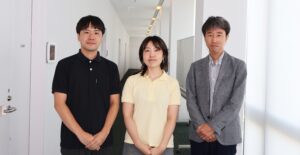DaigasグループDaigasグループ発U-35世代のコミュニティ「TAY」から生まれた新規事業『はじまり はじまり』

社会課題に向き合う若手世代が、立場や組織を越えてフラットに集まり、思いを共有し合う場が広がりつつあります。その一つが、大阪ガスネットワークが社会貢献事業として運営する「Talkin’About Youth(TAY)」です。2023年5月にスタートしたこのコミュニティは、35歳以下の世代を対象に、社内外を問わず誰もが参加できる開かれた場所を目指しています。
毎月のトークイベントでは、NPOの活動家や新規事業に挑むイントレプレナー、表現を通じて社会に発信するアーティストなど、多彩なゲストが登壇。参加者は彼らのリアルな経験や思いに触れることで、自分自身の課題意識を言葉にしやすくなります。そこから小さな共感や気づきが生まれ、やがて新しいアクションやプロジェクトへとつながっていきます。
本稿では、このTAYの成り立ちや活動内容、そしてそこからどのように新規事業が生まれたのかについて、発起人の一人である吉住さんにお話を伺いました。
Talkin’About Youthとはどういったコミュニティなのか
まず、「Talkin’About Youth(以下、TAY)」とはどういったコミュニティなのかを教えていただけますか。

Talkin’About Youthは、2023年5月にDaigasグループ(大阪ガスグループ)の一社である大阪ガスネットワークの社会貢献事業としてスタートしました。対象は35歳以下、いわゆるU-35世代です。Daigasグループ社内の社員だけでなく、社外の若手も誰でも参加できる、開かれたコミュニティになっています。
活動の中心は、毎月1回のトークイベントです。社会課題に対して行動している方をゲストにお招きし、ご自身の思いや背景、展望まで語っていただきます。例えば、子育て支援に取り組むNPOの方、新規事業に挑むイントレプレナー、表現を通じてメッセージを発するアーティストなど、本当に多彩な顔ぶれです。その話を聞いた参加者が「自分もこんなことにモヤモヤしていた」と気づき、声を出しやすくなるのがTAYの特徴です。
トークイベントでは規模を追いません。大人数を集めて満足度を測るのではなく、ファシリテーターが「本当に話を聞きたい」と思うゲストを招き、その熱量に共感する人が数人でも集まれば十分に価値がある。人数よりも「思いの深さ」や「共感」を大事にしているのがTAYらしさです。
TAYのコミュニティの特徴を教えてください。
一番大きな特徴は、「好奇心の前にはみな平等」(※出典:京都大学総合博物館 塩瀬准教授)といった思いで、誰にでも平等に機会が開かれていることです。TAYは「社会課題解決」をコンセプトにしていますが、特定の事業や人を応援するためではありません。参加者は全員フラットな立場で、それぞれの関心や行動が尊重されます。その結果として私から新規事業が生まれましたが、新規事業であるかどうかはTAYの本質ではなく、あくまで一つのアウトプットにすぎません。
また、アウトプットを「グラデーション」で捉えているのも特徴です。例えば「子どもの貧困を解決する事業を立ち上げたい」と考えて実現させた人と、「そのテーマの本を読んで共感した」と話す人。事業と意見の表明というアウトプットの種類は違っても、どちらも社会課題に向き合うアウトプットとして価値があります。個人の熱を大切にしていて、小さな共感が積み重なることで大きな動きにつながる。そうした循環を意識しています。
イベント後も各自がLINEでつながり、分科会やサークルが派生していくのもTAYらしいところです。飲み会やランニングやリトリートといった気軽な活動から、事業開発に関する勉強会の開催、昭和町に私設図書館をつくるようなプロジェクト、会社での新規事業の立ち上げまで、さまざまな取り組みが自発的に生まれています。
まとめると、TAYは「社会課題をテーマに、U-35世代がフラットに参加し、多種多様なアウトプットを等しく価値として認め合い、混ざり合う」コミュニティです。その柔らかさが、コロナ禍のあと、多くの若手にとって「もう一度前を向くきっかけ」になっているのだと思います。
Talkin’About Youthができた背景
そもそも、TAYはどういった経緯で生まれたのでしょうか。

TAYは、大阪ガスネットワークの社会貢献活動の一環として始まりました。少なくともDaigasグループには1980年代から社会貢献の歴史があり、障がい者や社会的養護を必要とする子ども支援、被災地支援、社員によるボランティアやNPOとの協働などを続けてきました。ただ、その多くは「企業の社会責任として社会に良いことをする」という従来型の活動イメージが強く、若手世代にとっては自分事になりづらく、距離を感じやすいものでした。その結果、意義は大きいのに若手社員の参加率は低かったんです。
時代とともに「社会貢献」よりも「社会課題解決」や「社会起業家」という言葉の方が若者に響くようになりました。課題解決が自分の成長やキャリアにもつながる——そんな「利他と利己が重なる感覚」が重視されるようになったんです。そこで従来の活動を見直し、「なんか良いことをしたいな」と青臭くピュアに思う若手が自然と集まれる新しい場をつくろうと考えたのが、TAY誕生の大きなきっかけでした。
吉住さんご自身は、この取り組みを立ち上げるにあたってどんな思いを持っていたのですか。
2018年に入社して以来、同世代や後輩を見てきて感じたのは「社会のために役立っている」という実感を持てる人ほど仕事を続けやすい、ということです。逆にその実感がないと成果や数字に追われていると感じて疲弊し、離職やモチベーション低下につながってしまう。入社直後は多くの方が「何かやりたい」という思いを持っているのに、数年経つとその火が小さくなり「やめます」「もうどうでもいい」となる。その違いを目の当たりにして、寂しいなと感じました。
一方で、生き生きと働く人は年齢を重ねてもずっと前向きです。私はNPO法人の活動もしていて、65歳を超える方々と接する機会に恵まれていますが、その経験から強く実感しています。「前向きであり続けられる」要素の一つも「自分が社会に貢献している実感を言語的な理解ではなく身体的な感覚として得られるような環境が身近にあるかどうか」だと思いました。だったら、その実感を取り戻せる場をつくればいい。しかも個人ではなく会社として提供すれば、持続性があり多くの人を巻き込める。そう考えて「U-35の若手が集まるサードプレイス」を立ち上げようとしたのが、私の思いです。
なぜ、そこから新規事業が生まれたのか
コミュニティ活動が中心だと思うのですが、そこから新規事業が生まれるのは興味深いです。どうつながっていったのでしょうか。
TAYの根本には「誰でも安心して一歩踏み出せる場をつくる」という考えがあります。そのためイベントの最後には「今日の話を聞いて自分ができそうなことは何か」を言葉にしてもらいます。小さな気づきからでも「試してみよう」と声を出すことで、自然に行動につながりやすいんです。
繰り返しですが、そこから生まれるアクションは幅広いです。読書会や趣味のサークルもあれば、図書館をつくる地域プロジェクトや会社としての新規事業もあります。
大事なのは「大きな挑戦も小さな一歩も等しく尊重される」という文化で、それが結果的に事業の芽を育てる土壌になっているのだと思います。失敗も成功も区別されず、思いを自由に外に出せる場だからこそ、事業化できるかどうかより先に「実現したいこと」を口にできる。
その言葉に一人、また一人と共感が集まり、やがて「自分の思い」が「みんなの実現したいこと」へと変わっていく。
そうして少しずつ形を持ちはじめたものが、会社に持ち帰られてもつぶれることなく、やがて事業という形にまで育っていったのだと思います。
実際に新規事業に発展したケースを教えていただけますか。
私自身の例で言うと、わが子が生まれたことをきっかけに子育てに関心を持っていたことがきっかけです。TAYで起業家や大企業のイントレプレナーの話を聞くなかで「社会課題にビジネスの領域で挑める」「大企業でも新規事業を立ち上げられる」と実感しました。そこから「親子のコミュニケーションをもっと豊かにしたい」という思いと結びつき、新規事業のアイデアに育っていったんです。
どういった新規事業なのか
では、実際に生まれた新規事業について教えてください。

現在「はじまり はじまり」という名前で展開しているサービスです(WEBサイト:https://www.hajimari.app/)。簡単に言うと、子どもが選んだキャラクターや場所をもとにAIが絵本を自動生成し、親子で楽しめるサービスです。親と子のコミュニケーションをスムーズにすることを目的としています。
私がこのサービスを考えた背景には、自身の子育て体験があります。
子どもが2歳の頃、言葉やしぐさで一生懸命に気持ちを伝えてくれるのに、私自身の理解が追いつかず、思いを汲み取れないもどかしさを感じることが度々ありました。例えば、レゴブロックで首の長い形を作って見せてくれると、大人には「キリンかな」と見える。でも、子どもがイメージしていたのはまったく別の動物だったかもしれません。その違いに気づけずに「キリンを作ったんだね」と返してしまい、子どもが少しがっかりする。そんなすれ違いが積み重なりました。
そのとき支えになったのが絵本です。絵本の中には多様な動物や場面が登場し、子どもは自由に指をさして反応する。親も「これはどう思う?」と問いかけながら、自然に会話を広げられる。絵本は親子の間に入って、ちょうどよい情報量で対話を促してくれる存在だと気づきました。
そこから、「もしAIを使えば、子どもが興味を持った題材で、その場で絵本を生み出せるのではないか」と考えるようになりました。従来の絵本や知識は、大人から子どもへ与えるものという構造が前提になっています。けれども実際には、子どもが大人に与えてくれる感性や学びは計り知れません。ただし現実には、大人のリテラシー不足や忙しさによって、その豊かな表現を受け止めきれず、取りこぼしてしまうことも多いのです。
AIはそのギャップを補う手段になり得ます。子どものアウトプットをAIが物語として形にしてくれることで、大人がそれを受け取りやすくなる。物理的に絵本を大量にそろえることは難しくても、AIならその瞬間に物語を届けられる。そんな仕組みがあれば、親子の会話はもっと豊かになり、子どもの小さな思いが大人にもしっかり伝わるのではないか——そう考えて、このサービスを構想しました。
サービスの内容を具体的に教えてください。どのような機能が盛り込まれているのでしょうか。
「はじまり はじまり」では、子ども自身が主人公になります。子どもが気になる動物や場所を選ぶと、その要素を盛り込んだオリジナル絵本をAIが生成します。さらに、子どもがどんな言葉に興味を持ったのかを親にフィードバックする機能や、「読むときはこんな声かけを」と提案する機能もあります。
サービスは月額制のサブスクリプションで、2024年7月にローンチしました。家庭向けに提供を始めており、親子の「読み聞かせ」の時間を充実させるとともに、コミュニケーションに悩む親をサポートすることを目指しています。
コミュニティから広がる応援と連鎖
TAYの活動から生まれた新規事業については伺いましたが、他のメンバーはどう受け止めていたのでしょうか。
反応はとてもポジティブでした。「子どもに思いを持つ大人がもっと集まればいいね」「どう広めようか」などの声があり、まるで応援団のようにアイデアをもらいました。例えば「住んでいる団地の集会場にチラシを置いてはどうか」「うちのサービスと一緒にキャンペーンをしたらどうか」といった具体的な提案もあり、一つひとつ試すことができました。
自然に応援の輪が広がっていくのは、このコミュニティならではですね。
そうですね。TAYでは誰かが「やろう」と手を挙げたら全力で応援する、という空気があります。強制ではなく「応援するのが心地いい」というスタンスですが、結果的に自然と文化として根付いています。
吉住さん以外にも、新規事業の芽は出てきていますか。
いくつか動きがあります。例えば、大阪・昭和町のコミュニティスペースを借りて開いた私設図書館で、一箱本棚制度を取り入れ、本以外の表現も置ける場になっています。来場者から利用料をいただきながら運営しており、事業性も備えた取り組みです。
今回の私設図書館の立ち上げは、TAYの活動の中でどのような広がりや影響を生みましたか。
図書館が実際にオープンすると、TAYの仲間たちも「いいね!」「自分が企画する読書会をそこで開催しよう!」と応援してくれて、自然に支え合う空気が広がっていきました。TAYでは「誰かがやろうと言ったら応援する」という文化が根づいていますが、この取り組みもまさにその象徴だったと思います。
今後の展望と参加者への期待
最後に、TAYがこれから目指す方向性と、新しく参加する人への期待を教えてください。
まずは気軽に来てもらいたいです。「いいな」と思うことも「違うな」と感じることもあると思いますが、その反応を言葉や行動にしてもらえれば共感する仲間が必ず見つかります。無理のない範囲で発言したり、小さなアクションを起こしたり、事業を開発することに興味があるなら一緒に形にしてみたり。そうやって少しずつ輪を広げていければと思います。
同時に、TAYとしては大阪ガスの120周年を記念に「120人・120個のアウトプット」が生まれる場になることを目標にしています。その目標の連続性で、ゆくゆくは活動拠点も広げたい。今は大阪・グランフロントが中心ですが、各地の仲間とつながって10拠点に広げられればと考えています。ちょうど2028年は大阪ガスグループが「Daigas グループ」に名称変更してから10周年。そのタイミングまでに実現できればうれしいなと考えています。
また、今既に種類が増えつつあるアウトプットも10の領域で10ずつ尖った取り組みを生み出したい。小さな活動でも大きな事業でも、思いの熱量は同じです。そうした思いを大切にしながら、TAYが心地よいものであり続けられれば良いなと思っています。