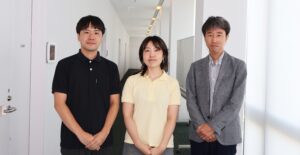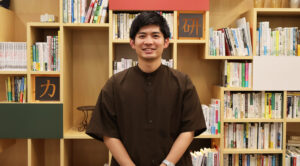日本板硝子株式会社「素材売り」を越える日本板硝子の新規事業開発。クリエイティブテクノロジー事業部門が挑む組織づくりと2030年への道

日本板硝子株式会社のクリエイティブテクノロジー事業部門で事業開発を担う生田 譲 氏は、事業開発推進部に所属しつつ事業企画室も兼務し、新規事業と組織開発という中長期的なテーマに挑んでいます。前所属の建築ガラス事業部での方針転換をきっかけに、組織的に新規事業に注力し、積極的に取り組むため現部署へ異動。現在、同社の全社方針として掲げられる「4つのD」(Business Development, Decarbonization, Diverse Talent, Digital Transformation)の一つであるビジネスデベロップメントを推進する中で、経営へのインパクトをこれから形にしていくという大きなチャレンジに取り組んでいます。
本記事では、日本板硝子株式会社が掲げる新規事業の実像や、事業開発の最前線で得られたリアルな学び、そして未来に向けた展望について詳しくご紹介します。
異動の背景とミッション——「商品開発」と「事業開発」の線引き
まず、自己紹介と現在のミッションについて教えてください。
日本板硝子株式会社の生田と申します。現在はクリエイティブテクノロジー事業部門で事業開発を担当しています。事業開発推進部と事業企画室を兼務しています。新規事業創造を軸に社内の事業開発の仕組みや人材育成・組織開発などの企画・推進を担っています。いずれもクリエイティブテクノロジー事業部門の事業大成長に向けて、自ら新規事業創出を行いながら、イノベーション人材の醸成を進めることが私のミッションです。

新たな部署で新規事業開発を担うことになった経緯を教えてください。
今年の6月までは建築用ガラスを扱う事業部で新規事業開発を担当していましたが、方針転換で既存事業内の「商品開発」へ軸足が移り、新規事業開発は取り組まない方針になりました。そこで、引き続き新規事業に携わるため、クリエイティブテクノロジー事業部門へ異動しました。
社外人財向けプログラム「beyond the Border」の仕組みと運営
「商品開発」と「事業開発」の違いをどう捉えていますか。
商品開発は「ガラス素材の提供」という既存のビジネスモデルを前提に、新しく機能付加した窓ガラス素材やガラス
素材を開発し拡販していくこととし、一方の事業開発は、ガラス素材の提供にとどまらず、サプライチェーンの上流・下流に踏み込み、デバイス化やサービス化など、売り方やモデル、チャネルまで変えていく取り組みです。強みであるガラス素材技術を活用・展開しながら、ビジネスモデルを変えることが重要だと考えています。
会社全体での新規事業の位づけを教えてください。
全社方針としては「4つのD」の中にビジネスデベロップメントが掲げられていますが、戦略や経営数字にどう織り込むかはまだ明確ではありません。収益拡大といったKPIに対して、新しいことに取り組む必要があるという認識のもと、クリエイティブテクノロジー事業部の中で私たちの部署が個別に事業開発を進めています。
注力テーマと組織のリアル——半導体/環境素材、2つの成長市場の課題にチャレンジ

半導体と環境素材を選んだ理由を教えてください。
半導体と環境素材を注力領域に据えた理由については、まず半導体領域における外部環境の変化が大きな契機になっています。AIの進展に伴い、半導体には大容量・大電力・発熱といった課題が顕在化しており、電気信号を光に置き換える流れが強まっています。当社はガラスの透明性という強みに加えて、レンズに代表される光学関連の技術アセットを保有しています。こうした光技術は、電気から光への転換という産業の潮流と親和性が高いと考えており、その適合性を踏まえて技術開発とマーケットリサーチを並行して進めています。端的に言えば、自社の技術アセットを最大限に活かしうる領域であり、かつ市場の構造変化が追い風になると判断しているためです。
また、領域選定の考え方としては、手持ちの強みを基点にしつつ、将来像からのバックキャストを重ね合わせています。つまり、今ある技術で戦いやすい場所を選びつつ、数年先に市場が向かう方向を先に描いて、そのゴールから逆算して今やるべきテーマを決めている、ということです。
現時点での主な課題と、その背景について教えてください。
大企業あるあるですが、新規事業に取り組む人材リソースの不足です。新しい技術を見つけても、マーケットリサーチや技術開発に人を十分に割きづらい状況があります。加えて、投資原資をどう確保するかが常に大きな論点になります。人材面、組織面においても事業開発実行を立ち上げている段階ということもあり、事業開発に必要なスキルが社内に十分に蓄積できていない状況でもあり、組織開発、風土醸成もこれからの課題になってくると感じています。
組織的な壁はありますか。
2030年の大きな営業利益目標に対して、従来の「素材を売る」という前提だけでは不十分だという共通認識が社内で広がっていることもあり、組織全体でも新しいことをやっていく必要性を持っているため大きな壁を感じていません。良い意味で兼務体制なので横の連携は取りやすい一方、リソースの分散と実行責任の所在が不明確になりやすいため、テーマごとに主担当を明確にしています。
仕組みづくりと3年後の到達点
新規事業スキルをどう育て、組織に根づかせますか。
新規事業のスキルを育てて組織に根づかせる手段として、ビジネスコンテスト(ビジコン)を実施し用途考えています
。ここでは、社内アセットや自身のやりたいことの見つめなおしから新規事業のアイデアを構想する力に加え、個々の
仮説検証を繰り返す行動力を中心にとしたマインド・行動スキルの底上げを考えています。経験者を着実に増やしながら「実行できる人材」の裾野を広げ、組織全体の底上げにつなげていきます。
同時に、事業性のあるテーマについてや「事業開発を続けたい」という強い意志を示した人が、フルコミットで事業開発に取り組める環境を整えます。ビジコンを“登竜門”とし、その先に“実践の場”を用意する二段構えにすることで、個人のモチベーションと事業の実装を両立させます。さらに、この挑戦を支えるために、社外での人脈形成やバックアップとなる研修も継続的に設け、挑む人が前に進み続けられるよう下支えします。
経営層とのコミュニケーション状況はいかがですか。
事業部門のトップとは月1程度でコミュニケーションを取っています。半年に一度、マネージャーやミドル、さらに上の経営層も交えた合宿のような場があり、意識づけと方向性の共有ができる風土が醸成されています。
社外との連携はどのように進めますか。
同様の課題に取り組む大企業やスタートアップと連携して事業をつくることに挑戦したいです。直近で走る二つのテーマはいずれも大学との連携で、素材×大学、技術×大学の相性の良さを活かし、技術の掛け合わせによる事業開発の実績づくりに注力します。
3年後、どのような状態をめざしますか。
人材育成では、事業開発を「やりたい/やってみたい」という人が1〜2人しっかり現れていること。事業では、プロセスをつくり取り組みを積み上げた結果、実際にキャッシュを生む事業が1〜2つ立ち上がっていることをめざします。

生田さんにとって新規事業開発とは何で、またその大変さをどう捉えていますか。
私にとって新規事業開発は、人脈を広げながら新しいことに挑戦でき、自分のやりたいことを実現しやすい環境です。好奇心を持って色々なコトに取り組める方にとっては、とても良いフィールドだと思います。正直あまり「大変だ」とは感じておらず、早く事業貢献・社会貢献につながり、取り組みが実績として認められれば良いという気持ちで続けています。
最後に、大企業で新規事業に挑む方々へメッセージをお願いします。
大企業で新規事業に挑戦できるのは恵まれた環境です。自由度が高く、必要なところには投資を受けられる場合もあります。大企業の影響力を活用すれば、新しいことに挑戦できる機会は多いはずです。物事をいろいろな角度から見て、今の環境での仕事を楽しんでください。
読者の皆様にお知らせがあれば教えてください。
産学連携と大企業同士の「技術起点」の共同研究~事業開発連携を中心に進めていきます。日本板硝子の持つ技術やチャネルを知りたい、興味があれば、連携による事業の取り組みをご一緒できればと思います。ご連絡は私あてで大丈夫です。LinkedInやFacebook Messengerでご連絡ください。
・Facebook
https://www.facebook.com/jo.ikuta
・LinkedIn
https://www.linkedin.com/in/%E8%AD%B2-%E7%94%9F%E7%94%B0-25826769/